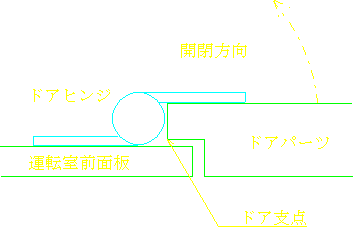| 2008年11月 運転室②
|
|
|
新しく設計した運転室パーツを組み立てた。運転室①でカットしたものを組み立てるだけのことだったがかなり難航した。 原因は前面扉を開閉可能にしたことにあった。単純な思いつきで開閉可能にしたことが裏目に出てしまったのだ。 |
|
|
まず問題となったのは前面扉のヒンジであった。ドアをきっちり閉めるため、運転室前面板に空けたドア穴に対して、ドア本体は1mm大きくカットしてある。これにより、ドアは室内側に開くことはない。 しかし、逆に言えばヒンジを裏からつけることができなくなる。実物のように表側にヒンジをつけなくてはならない。このサイズのヒンジがとても限られている上、ドア厚み分、段つきになっていなければならない。 |
|
|
|
|
|
さらに、旋回窓つきにしたことも凶とでた。実機の8620は前面窓のヒンジがボイラー側についているものもあれば、運転室側面板側についているものもある。実機やセントラルのパーツから判断した位置はかなり側面板側に寄っているため、ヒンジはボイラー側につけたほうが楽になる。 しかし、旋回窓付のドアーはボイラー側にヒンジをつけると、形状の関係で開閉できない。結局側面板側につけるしかなく、わずか9mmのスペースにヒンジを取り付け、さらに裏側(室内側)には側面板接合アングルをつけなければならない。 さて、どうするか・・・と考えているうちに8ヶ月過ぎてしまったのである。 とりあえず運転室を構成する主要なパーツ、すなわち前面板、側面板、後面板を接合してみることにした。だめならドアを開閉できないようにすれば良いだけの話である。 |
|
|
|
|
|
それぞれのパーツは真鍮アングルで接合する。実機8620の運転室はリベットで組み立てられているため、模型にする場合にはとても楽になる。 前面板・後面板を半田付けにした理由は、前面板の扉のヒンジの関連があるからである。ま、接着剤でも良かったのだが。 前述したように前面板の側板取付部分は幅が9mmしかないので、10×10のアングルを使うと1mm、ドア部分(後面板は窓部分)にはみ出てしまう。最初にこのはみ出る部分をカットすることにした。後面板はドアがないものの、やはり窓にアングルが被るのでカットする。 |
|
|
|
|
|
アングルにより組立 |
窓と重なる部分はカット |
| 写真のように被る部分をエンドミルで削り落とした。フライス盤があるとこのような作業はあっという間に終わる。サビがひどいがこれはアングルのハンダ付けの際にフラックスを使ったためである。内側なのでどうということはない。
|
|
|
組上がった運転室に前面ドアを取り付ける作業に移った。 最初にヒンジを探すことにした。以前からホームセンターに小さな蝶番があることを知っていたので、一番小さいサイズを購入し、一旦分解して軸を抜き、片方を裏返して組みなおした。これで軸部分の厚みだけ段差が付くことになる。そして裏返したことで軸からはみ出してしまった部分を糸鋸でカットした。 出来上がったヒンジをドア側に真鍮クギをリベット代わりにして取り付けた。リベット接合した理由は簡単で、ネジ止めするだけのスペースが取れなかったからである。 |
|
|
|
|
| 写真を良く見るとヒンジの上に銅の色をしたネジサイズの円が見える。これは穴あけ位置を間違えて銅丸棒で穴埋めした跡である。とりあえずドアの取り付けが終了した。ハンドル部分はまだ考えていないので後回し。 | |
|
|
|
| 実機の運転室後面板は天井部分で繋がっている。ライブの場合は後面板・屋根は運転の邪魔になるので一部カットするのが一般的である。私は取り外し可能な後面板にした。こうしておけば工作中は箱になるので強度が得られ、運転する場合には取り外しておけばよい。意外と後面板は邪魔にならないかもしれない。 | |
 |
 |
| 枠になった運転室(公式側前より) | 枠になった運転室(非公式側後ろより) |
| 運転室は飾りであるが、操作系との絡みが出るので、設計は意外に難しかったりする。今回は逆転機の引き棒の位置とドアの関連もあり時間がかかってしまった。屋根も操作系に影響が出る上、目立つところなので装飾も面倒である。
|
|