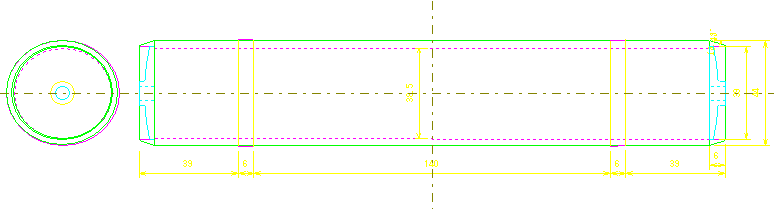| 臨時増刊
エアータンク
|
|
|
せっかくの二段ランボードにもかかわらず、キットにはエアータンクが入っていない。オプションで購入できるのだが、自作することにした。 過去何度か工作記で書いているが、この機関車は「縮尺何分の一」と言うことができない。おおよそ9.3分の1というのが私が計算した縮尺である。全幅を縮尺調整しているため、単純ではないのである。その弊害でランボードの幅員が縮尺よりもかなり大きく、この点を私はとても残念に思う。 実機のエアータンクについてだが、8620、9600、C51、D50等の大正機から昭和一桁までは(もちろんそれ以前の機関車も)近代機と異なったタイプのエアータンクが付いている。タンクの鏡板部分が絞り込まれており、きれいな流線型をしているわけではない。またエアタンクは機関車の大きさによって規格化されており、数種類存在するようである。 鉄道史資料保存会発行の「8620型機関車明細図」にはエアーブレーキの図面が一部添付されており、幸いにもメートル表示である。(古い資料はインチ表示がほとんど)。明確な図面はなかったが、輪郭は表示されていたのでそれを縮尺比で出してみた。 エアータンクは全長・全幅とも9.3分の1で計算した。直径が全幅の縮尺よりも小さくなるが、全長とのバランスからこの数字でよいだろうということになった。計算した結果、奇遇にもセントラル鉄道で販売しているものと直径が同じになった。
|
|
|
エアータンク図面 |
|
|
が、材料の関係で外径は44.5mmになった。材料は外径44.5mm、板厚3.0mmである。材料屋に44.5×3.0×470の真鍮パイプがころがっていたのでこれを購入した。 図面上のエアータンクバンドは切削加工で浮き彫りにし、ステーを介して機関車へネジ止めする。どうせランボードの陰になって見えないから問題ないだろう。端面の外径が44mmになっているのはそのためである。つまり、バンドは0.25mm浮き彫りになる。バンド部分の外径は44.5mmになり、材料の外面をそのまま使うことになる。 |
|
|
材料と寸法が決まれば工作である。まず、全長470mmのパイプをちょうど真ん中でカットしなければならない。仕入れた材料の全長がギリギリなので気を使う。 カットした後は購入したばかりの固定触れ止めを使用して端面切削し230mmに合わせる。その後、端面の内径を中繰りバイトで39mmまで拡大して鏡板の取り付けフランジにする。 固定触れ止めが妙にきれいで美しい!エアータンクの切削はパイプ切削の要素が全て含まれていた。旋盤の練習にはもってこいだ。 |
|
 |
 |
|
内径を39.0mmに拡大 |
外径を0.5mm切削する |
| 9.3分の1とは言っても、さすがライブである。エアタンクの大きさはキンチョールよりもやや細いぐらいのサイズになった。 | |
 |
 |
| 切削を終えたエアータンク | でかい、重い |
| これが終わったら今度は鏡板の工作である。実機の写真を見る限りとても大きなRになっているようなので、刃物台を10度傾けてテーパー切削で仕上げた。中央には5mmの穴を開けてあるが、この穴には冷却管との接合ユニオンを植え込むつもりなので、もう少し実感的なることだろう。冷却管は3.5mmの銅丸棒を使用する予定。 | |
|
完成したエアータンク |
|
|
|
|