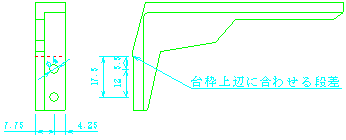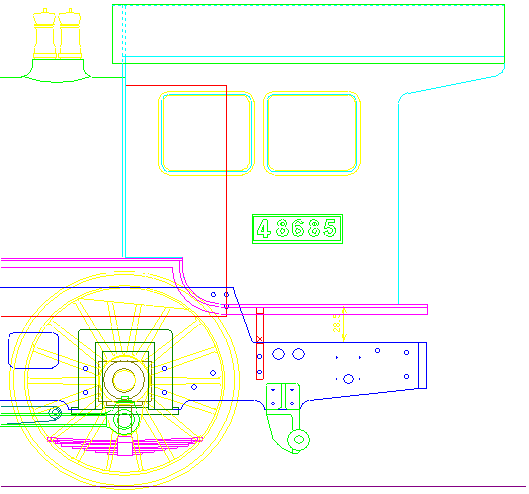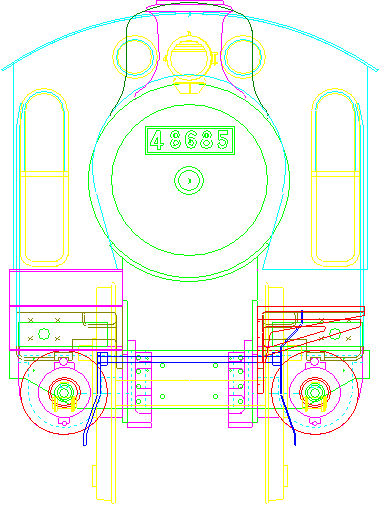| 2005年9月 第15回頒布 ランボード-①
|
|||
|
この機関車は実機の8620で言う2段ランボード・ショートキャブと呼ばれるタイプである。設計図は加筆修正が加えられているが、公差が大きく設定されているため加工寸法がよく分からない。 板台枠の機関車は台枠側にランボードが付くため、逆転軸受けの取り付けもランボード上で行なわれる。さらにランボードは運転室床板につながり、逆転機の取り付けベースにもなる。これらはバルブギアに影響を与える部品になる。下段は動輪にかぶるので、動輪カバーの取付や、逃げ加工も確認する必要がある。 この作業はかなり・・・死ぬほど面倒だった。 予定している8620の形態は空制化後になる。ランボード(運転室床板も含む)の上・下に載る部品を掲載すると以下である。 |
|||
| ① | デフレクター | ⑥ | 梯子 |
| ② | ルブリゲーター | ⑦ | 逆転軸受けカバー |
| ③ | 単式コンプレッサー(ダミー) | ⑧ | 逆転軸受け |
| ④ | 動輪カバー | ⑨ | 逆転機 |
| ⑤ | エアータンク(ダミー) | ⑩ | 冷却管(ダミー) |
|
これらの取り付け位置をCAD上で確認しながら同時に各パーツを採寸した。単式コンプレッサーは自作する予定だが、可能であればドンキーポンプを組み込めるようにしたいものである。 一般的に実機の8620や9600、D50、C51のような大正機はランボードが網目ではなく、普通の平板が使われている。網目ランボードになっているものもあるが、これらは末期に交換されたものである。 つまり、エアコンプレッサーの取り付けスペース分、左右のランボードの段がずれている。非公式側のほうは動輪が非常に良く見えて好印象である。設計に当たって左右の違いも再現することにした。ちなみに、送られてきている部品は左右とも公式側(エアコンプレッサー搭載側)の長さになっている。 |
|||
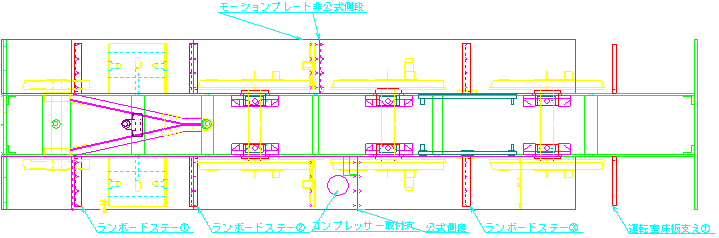
機関車上面図 |
|||
|
段の位置を左右で変更すると作り直しになってしまう。どうせ作り直すなら動輪舎から購入した網目板が残っているので、これを利用して新製することにした。動輪舎の網目板は入手できる唯一の鉄板プレス製なので、塗装の面で非常に有利である。とにかく真鍮はプライマーを塗ってもすぐにはがれてしまうので厄介。 ランボードを新製するために純正の部品を採寸したが、「現物合わせ」主体で作られており、あちこち辻褄が合わない。特にフロントデッキのエプロン部分は全く使い物にならない。上図面で「ランボードステー①」に該当するところだが、前端梁との取り付け位置が指定されてしまっているので、それに合わせてエプロンを取り付けるとステーと台枠の穴位置があわなくなってしまうのだ。 結局、すべてのランボードを新製することになった。動輪舎の網目板はプレス加工で穴を開けにくいので、今回もレーザーカットで行ない、穴あけ位置も最初から加工することにした。ランボードの設計は機関車上回りの印象を左右するとても難しいところである。 紫線はランボードの形状。赤はランボード・運転室床板のステー。ランボードはすべてステー上で分割する。一番の理由はバルブギアの調整のためである。ランボードステー①と②の間の板は簡単に外せるようにしておかなければ、バルタイがとれなくなる。 なお、図面では省略しているが、ランボード下段は第一動輪の逃げを加工しなければならない。純正のランボードは動輪逃げ加工済みになっていたが、動輪の横動を見込んでいないため、そのまま取り付けるとバランスウェイトがランボードに干渉する可能性が高い。 |
|||
|
ランボードを支えるランボードステーは左右3箇所ずつ、床板を支えるステーは左右1個ある。ランボードステーは鋳物、床板ステーはレーザーカットである。 作図にあたってまず基準となるランボードステーの採寸をおこなった。取り付け位置が明確に指定されているものがひとつあり、説明書によるとこのランボードステーを基準に他のステーの穴位置を確認するようになっていた。このランボードステーは前から3番目になり、上段側のステーになる。(上図面参照)。 |
|||
|
ランボードステー③ |
|||
|
ステー③は台枠取り付け面に段付き加工がされており、これによって上段ランボードの位置が決定する。台枠には取り付け穴があいているので、CAD上で重ねて穴あけ位置を確認したあと加工した。図面の数値が読みにくいが段差から5.5mm、12.0mmのピッチである。 下段のステーは全て基準値が分からない。当初前端梁から数値を追っていこうと考えたが、よく見るとモーションプレート上面がランボードステーをかねているようなので、既に取り付けられているモーションプレートから下段のステー取り付け位置を求めた。 |
|||
|
運転室床板は逆転機が取り付けられる。そのためシビアな取り付けと剛性が必要になる。また、床板の前部は大正期独特のR加工がされており、このRは運転室側板のRと一致しなければならない。 オリジナル設計は直線ランボードであるため、運転室床板は台枠上面とぴったり一致するが、二段ランボードになると、運転室床板の高さが後台枠の上面と一致しなくなる。つまり、段が付いた分、後台枠上面との間に隙間(28.5mm)ができるわけである。 |
|||
|
|
|||
|
逆転機は運転室床板に取り付けられるため、床板の取り付け位置が高くなると、逆転機の梃子比が変更になる。ちゃんと変更されているかどうかは今後確認しなければならない。 設計図によると後端梁と床板を固定するために1.6mmの鉄板を切り出し、アングルを介して固定するように指定されていたが、配管関連の自由度を広げるために後端梁は実機を参考にして作り直した。簡単に言えば、後端梁の上辺に28.5mmの枠を追加してレーザーカットしたものである。上図面は変更前の図面である。 |
|||
| 結局、8月・9月と図面制作で終わってしまったが、毎回この面倒極まりない作業を「やっていて良かった」と労ってくれる発見がある。今回の発見はなかなかビッグだ。純正部品をそのまま組み立ててしまうと最後に泣きを見る強烈な「ズレ」を確認した。 | |||
|
機関車前面図 |
|||
|
図面を見ていただければ分かると思うが、運転室前板(水色線)のボイラー切り取り部分が10mmセンターから上にずれている。これを知らずに組み立てると、最後の最後でボイラーケーシングと運転室の間に10mmの隙間が空くことになる。 当初、私が間違えているのではないかと側面図と比較してみたが、何度吟味しても同じ結果が出てしまう。なぜならボイラー中心と運転室前板切り取り中心を合わせると、運転室がランボードよりも10mm下に位置することになり、取り付けができなくなってしまうからだ。 いずれにせよ、ランボードの取り付けは運転室の取付位置まで確認しておかなければならないほど位置ぎめが大変だったということだ。 |
|||