|
煙室戸-① 煙室戸はバルクにしてもよかったのだが、一応開閉式にした。 私が今回のコッペルに乗せる予定のボイラーは煙官掃除が不要なので、煙室戸からブラシを入れて云々・・という作業は必要ない。 そんなわけで煙室戸は開閉式にした。想像以上に難しい工作だった!
|
|
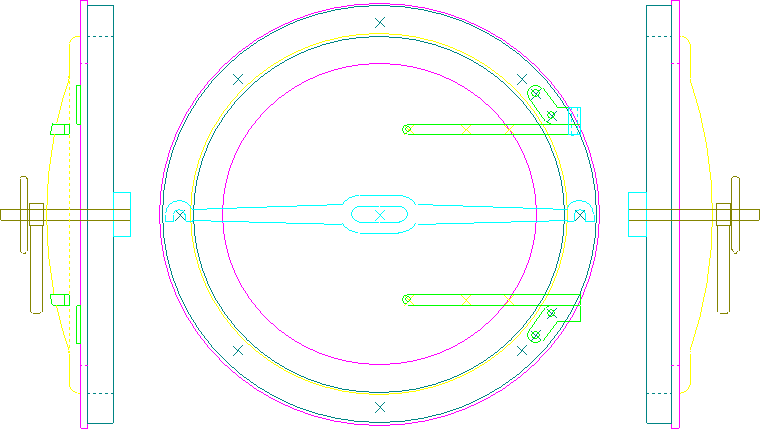
煙室戸組立図 |
|
|
前回紹介したケーシングはそれだけで強度を持っている。ボイラーケーシングと煙室部分は一体になっているので、まずはケーシング内径部分にきっちりはまるフランジリングを加工した。図面の深緑の部品である。 しかし、旋盤でまわすとどういうわけかリングが偏芯している。レーザーカットは偏芯するほど精度が低くないのでおかしいな・・・とCAD図面を確認してみた。 すると、中心点が0.5mm狂っているではないか!長時間の作図は眼を悪くする。こんなミスが結構出ているのである。仕方がないので再度外注しなおした。このように外注をしなおすとそれが仕上がるまでにまたタイムラグがでてしまう。その待ち時間を利用して8620を作っているのである。 リング外径をわずかに切削してケーシングに叩き込むぐらいの硬さに仕上げた。さらにショットで打ってある煙室戸受けリング(紫線)との締結ボルト穴加工をしておいた。あらかじめショット加工で8箇所均等割にしてあるので、煙室戸受けリングおよびフランジリングとも写し開ける必要はなく別々に加工できる。 煙室戸受けリングも同様に穴あけして準備をしておいた。煙室戸受けリングとフランジリングの固定はM2.6六角ビスを使用した。実機は大きなリベットで固定している。蝶番けの穴は強度が必要なので3.0mmボルトにした。この穴もレーザー加工の段階でショットしてある。罫書きは不要。 丸物に罫書きをするのは非常に難しいので最初の部品発注の段階でここまで考えて作っておくと後々楽である。 煙室戸はどうするか?Y氏は中華なべを利用して上手に仕上げられた。 もちろん先ほどの記述のとおり、かんぬき穴、蝶番固定ビス穴はあらかじめショットしてある。穴あけのジグを作る必要もない。 コッペルの煙室戸は国鉄型の煙室戸とだいぶ異なり、周りの部分は平坦で、途中から中央に向けて盛り上がる。これはかなり難しい加工になるだろう。ちなみにOSコッペルはプレスで作っているようだ。
|
|
|
|
|
|
写真でも煙室戸周囲に平面部分と盛り上がり部分の境界が確認できると思う。ニイザキモデルのコッペルも見事な煙室戸だった。これらに近づけるように努力する。 平べったい物をチャックするのは非常に難しい。ワークも大きく、外爪にしても三ツ爪チャックが使えないので、4ツ爪で加工した。材料はリングと同じく12mm鋼である。一番外側の薄いところは4mm弱になるので、チャックの咥えしろを4mmにした。 当初、煙室戸の材料裏側にヤトイをつけて加工しようとしたが、ボール盤で開けたセンター穴が傾いて開いておりうまく行かなかった。時間をかけて4ツ爪にセットし、全部の加工を終えるまでは外さないようにした。結果的には4mmの咥えしろでもなんら問題はなかった。 第一段階は旋盤で段々に加工する。荒削りである。
|
|
|
|
|
|
段々に加工 |
拡大写真 |
|
実はこの切削に3日間かかっている。12mmの鉄板を最大8mm近く削るというのは結構大変だった。というのも、私の旋盤は最低回転数が120/minと速いため、切削オイルが煙になって部屋に充満してしまうのである。 嫁さん曰く、「部屋に霧がかかっている」と・・・。 SS400はかなりネバイ。切削感覚はアルミに近い感じだ。やわらかい材料が必ずしも加工を楽にするというわけではない。 第二段階はここからバイトをハイスに変更して少しずつ段々を消した。直剣バイトの刃先形状を利用して角を少しずつ削る。 第三段階は刃物台に角度をつけて多角形に削りだす。しかしバイトで削れるのはここまでだった。 第四段階では手バイトで削りだした。この煙室戸は先に紹介したとおり、おわん型ではなく、縁から盛り上がるところは逆Rになるので、この部分の加工が非常に難しい。ひたすら半丸ヤスリで削りだす。 第五段階でようやくサンドペーパーの登場である。この時点で私は完璧だと自己満足していたが、後に塗装をして荒が判明し、再度旋盤にチャックするハメになった。
|
|
|
|
|
|
第五段階終了時 |
煙室戸受けリングと位置決め |
|
写真に残すことができなかったが、第五段階が終わったあと、煙室戸を裏返して慎重にチャックし、裏を0.5mmほど削って段つき加工した。これは煙室戸受けリングと煙室戸をぴったり位置決めするためである。 上写真で煙室戸腕取付用のショット穴位置が確認できると思う。 |
|




