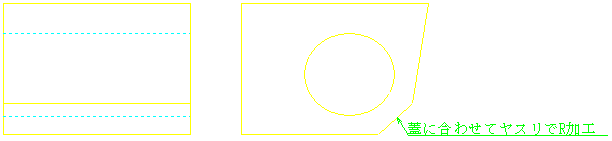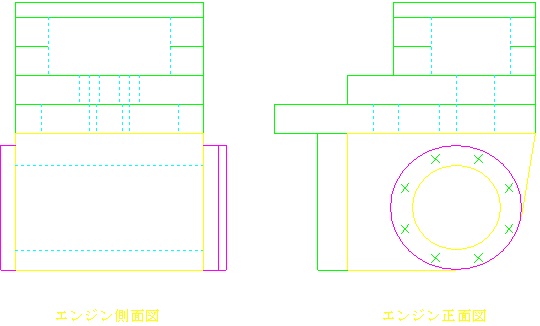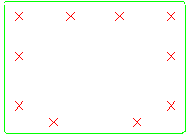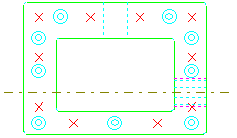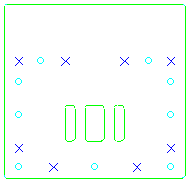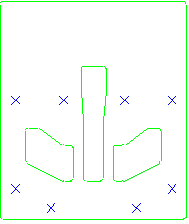| エンジン-①
シリンダー本体はデンスバーからの削りだしで製作した。もちろん外注である。 自分で鋳物を切削(ボーリング)して巣が出てきたなら「ああ、しょうがない。また鋳物から削るか!」で済むが、外注するとそういうわけには行かない。「巣」がでようがでまいが機械加工業者は関係がないのでそのまま代金を支払った上で使えないというリスクがある。 外注するにはデンスバーのほうがリスクが少ない。外観だってケーシングで覆うことを考えれば諦めがつくというものである。シリンダー本体の外観にこだわるのはパンツにまでおしゃれをするようなものである。私個人はそのようなおしゃれは大歓迎だが! |
| さて、デンスバーから削りだしたシリンダー本体はフレームに接合する面とバルブチェストの接合面が正確に直角でなくてはならない。外注しているのでさすがのできばえである。送られてきた状態の写真を撮り忘れたので簡単な図面を・・・ |
|
側面図 正面図(公式側) デンスバー削りだし・シリンダー本体 |
|
シリンダー外側はR加工しなくてはならないが、外注では荒削りだけお願いした。これをやすりでしこしこ仕上げる。ドレンコックやケーシング用の穴を開けるにはR加工する前の方が都合が良いので、シリンダー外側のR仕上げは一番最後にまわすことにした。しばらく見栄えが悪いままになる。 今回は、とにかく穴あけとタップたてばかりやることになる。 |
|
Y氏の設計では、台枠にシリンダーの取付位置を決めるためのガイド穴が設けられている。給排気ポート板の一部が台枠にはまり込み、位置決めできるようになっている。 そのため、まずはシリンダーにバルブチェストとポート板の取り付け穴を空け、その後台枠との固定穴、そして最後にシリンダー蓋穴を開けることにした。 本機関車は旋盤もフライス盤も購入せずに作れないものか?が設計の大きな目標になっている。エンジン関連は以下のような積み重ね構造で構成されている。板厚は一番上の蓋を除いて、すべてレーザーカットの限界、12.0mm鉄板である。バルブポートは後ほど解説する。バルブ室蓋は6.0mmを使用している。 まずは、これだけの鉄板を積み重ねてボルト止めするということをご理解いただきたい。 エンジン正面図の左側には板が飛び出ている。ここが先ほど書いた台枠に刺さり、位置決めとなる部分である。前回のサイドロッド取付写真を参照にしていただくと分かるが、台枠には長方形の長穴が開いている。 エンジン関連の構造は本当に良くできている。ある人はこの構造を見て「TFT回路のようだ」と絶賛した。Y氏オリジナルの簡単で効率の良いすばらしい設計である。 |
|
|
|
これらを締結するボルト穴位置を決めなくてはならない。実は私はこの穴の位置をしっかり検討しなかったため、2回も作り直した。12.0mmのレーザーカットは高価で、数万円のお金を捨ててしまった。この教訓を次に生かすしかない。 穴の位置は複雑で色分けして考えないと頭の中がぐちゃぐちゃになる。上の図面を参照に・・・・ |