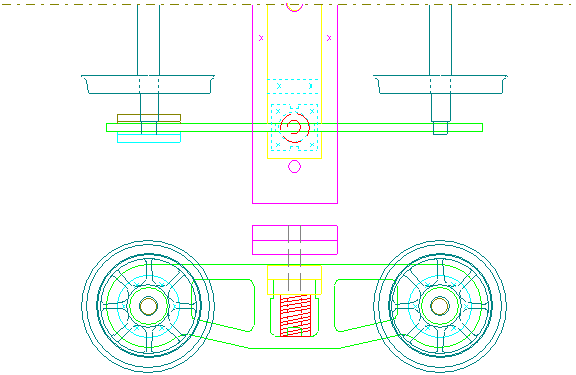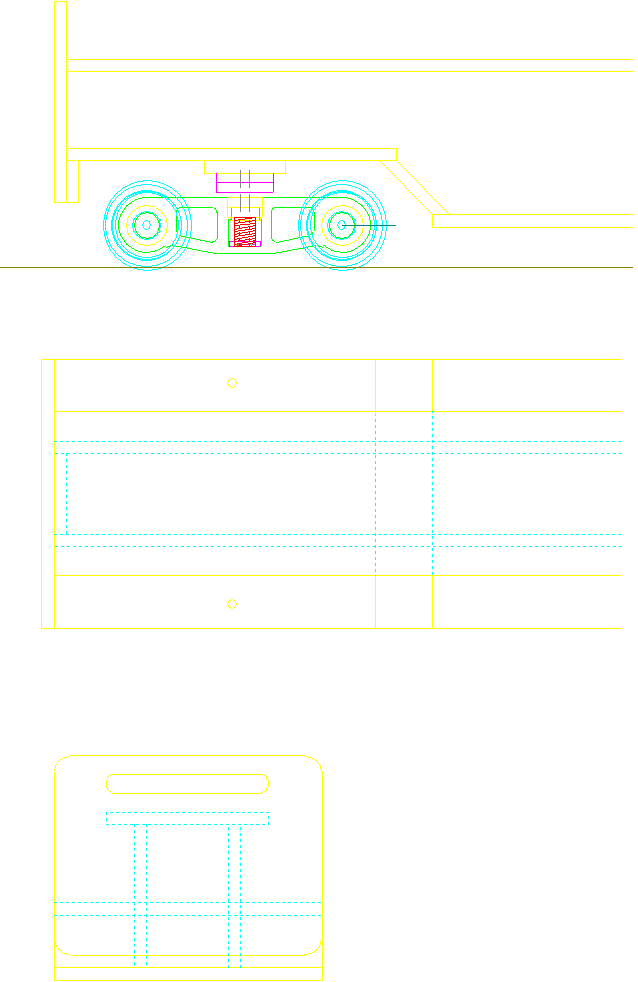|
2010年7月 乗用台車の製作① ライブスチームにかかわってから今年で10年を迎えるにもかかわらず、乗用(運転)台車を持っていない。 現在は特定のクラブに所属していないので定期的にライブを運転することはない。しかし、運転会に出かけるときには自分のものを持っていかざるを得ない。 最近子供がライブの楽しさに目覚めてくれたので、今後8620の完成した暁に乗用台車がないのではこまる。 さて、作ると決めたのは良いが、設計を始めたらとても難易度が高かった。 乗用台車は実際に人を乗せて走るため、全幅、全長、重心、安全性の基準をどこに置けばよいのかわからないのである。 こればかりは実際に統計をとって寸法を決定すべきことなので、他の人の製作したものをあちこち測って決定した。 今回、私はご近所に在住の師匠であるN氏に相談の上で設計を進めることにした。 乗用台車を製作する上で以下を条件とした。 |
|
| ① | 台車はそれなりの見栄えのものにする |
| ② | 車輪の径は102mmとし、ホイールベースは国鉄型台車の寸法に近づける。 |
| ③ | 保管・運搬を考慮し、台車を簡単に取り外しできる構造にする。 |
| ④ | 材料は合板を使用する。 |
| ⑤ | 以上を満たした上で、可能な限り簡単に作る。 |
|
⑤を実現するなら、①と②は無視すべきである。しかし、乗用台車の安定性を高めるために車輪径を小さくすると、いかにも乗用台車と見えてしまうのが悲しい。 運客を目的とした乗用台車に実機のような見栄えを要求することは間違っているかもしれないが、すこしでも実物に近づけたいものである。 実際、車輪径102mmの乗用台車は機関車とのバランスがよくかっこよく見える。 |
|
|
結局、形状は板台枠とベッテンドルフ型をいいとこどりした。 |
|
|
|
|