| 図面の検分
|
| 2014年3月に品物を手に入れてから1年以上たってようやく図面を検分できる状態になった。最初に全ての図面をスキャナーで取り込みPDF化した。
私はOSのT−5、セントラル鉄道8620だけでなく、資料関連もすべてデジタル化している。これでどこでも見ることができる。特に図面は工作中に見ると汚してしまうのでその都度プリントアウトしたほうが効率が良い。 その後、必要に応じてCADで図面を引きなおす。 |
| 8620の工作が滞っているが、その時間を図面作成に費やした。 ろく工房のコッペルはさすがと言うか・・・当たり前と言うか設計精度はほぼ完璧である。ほぼ・・というのは一箇所おかしなところがあったためだが、それぞれのパーツの取付位置、部品寸法は適切であり、整合が取れている。 ろく工房の販売当時の加工状況がどの程度だったのか全くわからないが、動輪舎のように機械加工が不要ということはなさそうである。 たとえば、煙突と煙室の接合面は全く旋削されていない。コッペルのような煙突の長い機関車は煙突の垂直度を追い込むのはとても難易度が高い。煙室台についても同様であり、罫書きの基準となる底面はミリングしてあるが、肝心なボイラーとの設置面は旋削されておらず、ここも加工難易度が高い。 機関車の工作状況から判断すると、前オーナーは台枠とボイラーの締結で挫折したようである。ボイラーの位置が定まらなければ逆転機構の工作もできず、まさしくここで終わってしまったのだ。 主要寸法がわからないので、加工寸法もわからない。わかったとしても加工は難しい・・・といったところだろう。 完成している下回りを見る限り、前オーナーの几帳面な性格が良く出ている。部品は仮組の状態であり、一部リベットで永久固定しているところもあるが、採寸した寸法と設計寸法はほぼ同一である。旋盤もフライス盤も持っていないと思われる環境で可能な限りの加工をしている。 工作が滞ってしまった部品は旋盤加工・ミリングが必要なところばかりである。工作機械がある、ないでは全く難易度が異なってくるだろう。 |
| とりあえず、工作に必要な部分を求めて作図をした。煙突等は一切書き込んでいない。半年近く品物を採寸して図面を作り上げた。 |
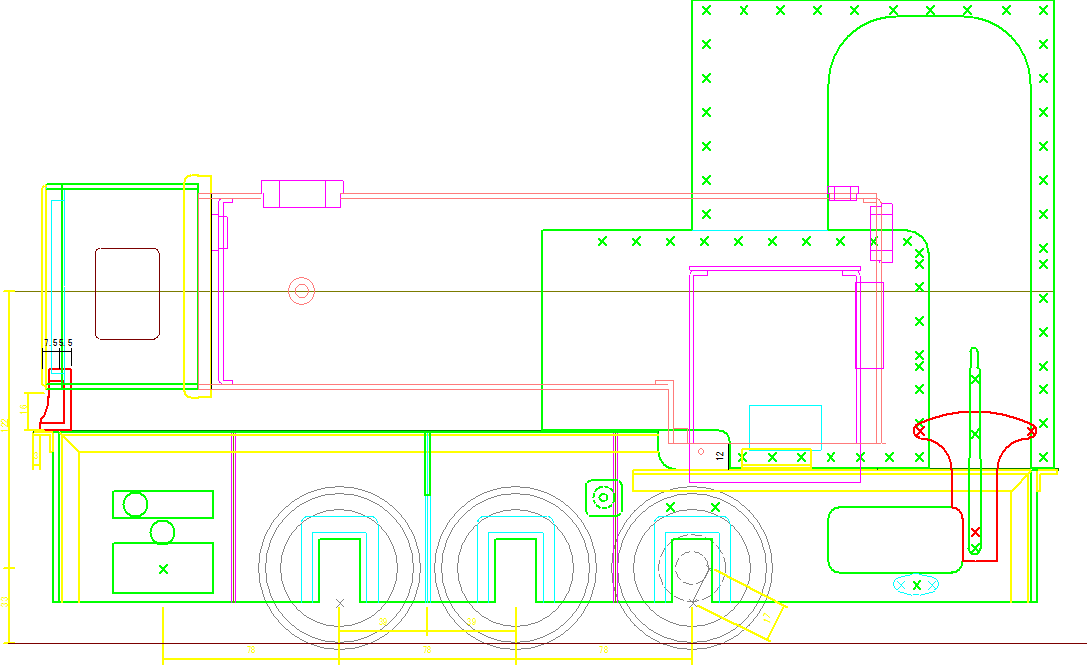 |
| 最初に三面図を作成したが、ボイラーはほぼ完成しているので図面と現物の一致を確認した。内火室周りは誤差が大きかったがこれはやむをえないだろう。内火室周りは灰箱の取り付けに影響するのでしっかりと採寸した。 8620の工作も同様だったが、ランボードの作図はかなり面倒である。特にコッペルは運転台側のランボードと台枠側のランボードが左右一体の一枚板になっており、このランボードに煙室台、板バネ、サイドタンク、ルブリゲータが取り付けられる。 図面の左端の赤い部品が煙室台である。砲金鋳物の一体物でランボード面のみミリングしてある。上辺よりも下辺のほうが前後方向に厚くなっており、余計な厚みの部分を利用してネジ止めする。ネジは下側から入れて前端張アングルランボード、ネジは煙室台を共締めして煙室台側でナット締めする。微妙な寸法が要求される。 この煙室台の位置でボイラーとその他のパーツの位置が決定するので、一番最初に煙室台から加工することにした。ランボード上面から煙室下部までの高さは16mmという結果が出た。 |
| 現時点で判明している問題 |
| 1.動輪の位相が狂っており、スムーズに回転しない。すでに組まれているブッシュを作り直すか再セットアップの必要がある。 |
| 2.煙室とボイラーがわずかにねじれてネジ止めされている。アライメントに問題がある |
| 3.ランボードの加工精度が悪いため動輪のイコライザー梃子の動きが悪い。 |
| 4.ルブリゲータの取り付け位置が判明しない |
| 5.煙室・ボイラーを固定する雌ネジ(ボイラー側!)にタップが折れて残っている |
| こんなところだろう。下回りの分解は後回しになるので他にもいろいろ問題が出そうである。 |
|
人の工作を引き継ぐと工作の苦悩が感じられて面白い。上の5など、ボイラーのタップが折れたときには相当へこんだはずである。あこがれのライブスチームを手に入れて楽しい工作がだんだん楽しくなくなる状況が目に浮かぶ。 工作派であれば誰でも一度は通らなければならない山である。 |
|
|